|
19世紀末期、産業革命によって動力の活用が盛んとなった頃、日本の主な輸出品目は生糸と緑茶でした。そのため、緑茶の生産に資産家が財を投じて参入し、大量に生産するために機械化が業界から望まれていました。この時代に、人生を賭けて開発に没頭した製茶機械開発の先駆者が高林謙三です。
 |
|
高林謙三氏
|
|
画像提供:静岡県茶業会議所
|
生い立ち
 高林謙三は、天保3(1832)年武蔵国高麗郡平沢村(現在の埼玉県日高町)の貧しい農家に生まれました。名を小久保健二郎といい(37歳の時に高林謙三と改名)、人一倍頭脳に優れ、学問好きな子供でした。 高林謙三は、天保3(1832)年武蔵国高麗郡平沢村(現在の埼玉県日高町)の貧しい農家に生まれました。名を小久保健二郎といい(37歳の時に高林謙三と改名)、人一倍頭脳に優れ、学問好きな子供でした。
 16歳で医学を志して隣郷の権田直助に漢方を学び、次いで佐倉藩侍医順天堂佐藤尚中の門に入り、西洋外科医術を修得します。下武蔵国入間郡小仙波村で医院を開業し、西洋医の権威として知られるようになりました。 16歳で医学を志して隣郷の権田直助に漢方を学び、次いで佐倉藩侍医順天堂佐藤尚中の門に入り、西洋外科医術を修得します。下武蔵国入間郡小仙波村で医院を開業し、西洋医の権威として知られるようになりました。
茶経営の乗り出す
 医者になった謙三は、明治元年頃には、かなりの財を成していたようです。
その頃、開港による輸入増加に対して、日本の輸出品は生糸と緑茶だけという状態でした。貿易の不均衡は著しく、「国益のためには茶の振興が急務」と一念発起した高林謙三は、茶園経営を始めます。
しかし、従来の手揉製茶法では、一人1日たかだか数キロしか生産できません。高林謙三は「緑茶の量産と生産費用の低減を図るためには機械化以外にない」と思い立ち、自ら私財を投じて製茶機械発明にその生涯を賭けました。 医者になった謙三は、明治元年頃には、かなりの財を成していたようです。
その頃、開港による輸入増加に対して、日本の輸出品は生糸と緑茶だけという状態でした。貿易の不均衡は著しく、「国益のためには茶の振興が急務」と一念発起した高林謙三は、茶園経営を始めます。
しかし、従来の手揉製茶法では、一人1日たかだか数キロしか生産できません。高林謙三は「緑茶の量産と生産費用の低減を図るためには機械化以外にない」と思い立ち、自ら私財を投じて製茶機械発明にその生涯を賭けました。
製茶機械の特許取得
 明治14(1881)年、謙三は、茶壺の中のお茶が、壺が動くたびに動くのをヒントに焙茶器の製作を試みますが、なかなかうまういきません。明治16年にやっと、味、色共に焙炉製より数段優るものができあがり、数回の機械改良を重ねて、明治17年、ついに焙茶器械を完成させました。謙三の発明した焙茶器械は、素人でも上手に良いほうじ茶ができ、茶の葉が粉になって無駄になることがなくなるため評判が良く、毎月何十台とよく売れました。
また、謙三は焙茶器と平行して、生茶葉蒸し器械、製茶摩擦器械の考案研究も行っていましたが、明治18年にこれらの器械も完成させました。 明治14(1881)年、謙三は、茶壺の中のお茶が、壺が動くたびに動くのをヒントに焙茶器の製作を試みますが、なかなかうまういきません。明治16年にやっと、味、色共に焙炉製より数段優るものができあがり、数回の機械改良を重ねて、明治17年、ついに焙茶器械を完成させました。謙三の発明した焙茶器械は、素人でも上手に良いほうじ茶ができ、茶の葉が粉になって無駄になることがなくなるため評判が良く、毎月何十台とよく売れました。
また、謙三は焙茶器と平行して、生茶葉蒸し器械、製茶摩擦器械の考案研究も行っていましたが、明治18年にこれらの器械も完成させました。
 謙三は、明治18年7月1日、日本に特許条例が施行されるのを待って直ちに出願し、同年8月には生茶葉蒸器械に専売特許証第2号が、焙茶器に第3号、製茶摩擦器械に第4号が下附されています。ちなみに、専売特許証第1号は、宮内省技師の発明した軍艦塗料なので、いわゆる民間発明家としての特許第一号は高林謙三の作品であるといえます。
この他、明治18年11月に改良扇風機で特許第60号を、明治19年3月には茶葉揉捻機で特許第150号を取得しています。 謙三は、明治18年7月1日、日本に特許条例が施行されるのを待って直ちに出願し、同年8月には生茶葉蒸器械に専売特許証第2号が、焙茶器に第3号、製茶摩擦器械に第4号が下附されています。ちなみに、専売特許証第1号は、宮内省技師の発明した軍艦塗料なので、いわゆる民間発明家としての特許第一号は高林謙三の作品であるといえます。
この他、明治18年11月に改良扇風機で特許第60号を、明治19年3月には茶葉揉捻機で特許第150号を取得しています。
自立軒製茶機械の失敗
 自立軒製茶機械は謙三の理想の機械で、蒸しから乾燥までの工程を順次に機械がやるというものでした。蒸器に搓揉機(さじゅうき・粗揉機の前身)と揉捻機を組み合わせて、これらの機械を経て出てきた茶が最後の乾燥機にかけられる、今のオートメーションの前身を目指したのです。
明治19年、医師を辞めて自立軒製茶機械の製作に没頭した謙三は、翌20年に満足のいく製茶をするまでに完成させました。 この機械の完成を喜んだ当時の埼玉県令吉田清英氏は、早速農商務省に報告し、全国の茶業者に対してこの機械の使用講演会を開催させています。その時、3府8県にわたり数千人が参加したといいますから、機械化に対する要望がいかに強かったかがわかります。講習生や見物人たちは、労力や経費が四分の一になるとの話を聞いて感心して帰っていき、その後各地から機械の注文が入りました。この功績をたたえて、明治21年に埼玉県から功労表彰が贈られました。 自立軒製茶機械は謙三の理想の機械で、蒸しから乾燥までの工程を順次に機械がやるというものでした。蒸器に搓揉機(さじゅうき・粗揉機の前身)と揉捻機を組み合わせて、これらの機械を経て出てきた茶が最後の乾燥機にかけられる、今のオートメーションの前身を目指したのです。
明治19年、医師を辞めて自立軒製茶機械の製作に没頭した謙三は、翌20年に満足のいく製茶をするまでに完成させました。 この機械の完成を喜んだ当時の埼玉県令吉田清英氏は、早速農商務省に報告し、全国の茶業者に対してこの機械の使用講演会を開催させています。その時、3府8県にわたり数千人が参加したといいますから、機械化に対する要望がいかに強かったかがわかります。講習生や見物人たちは、労力や経費が四分の一になるとの話を聞いて感心して帰っていき、その後各地から機械の注文が入りました。この功績をたたえて、明治21年に埼玉県から功労表彰が贈られました。
 ところが、自立軒製茶機械の購入者から苦情が相次ぎ、謙三が関係する埼玉製茶会社で製茶したお茶まで、この機械で製茶した茶の全てが不良品のため返送されてくるという事態になってしまい、自立軒製茶機械の失敗が証明されてしまいました。謙三は機械代金も満足に支払ってもらえず、経済的苦境に陥ってしまいます。 ところが、自立軒製茶機械の購入者から苦情が相次ぎ、謙三が関係する埼玉製茶会社で製茶したお茶まで、この機械で製茶した茶の全てが不良品のため返送されてくるという事態になってしまい、自立軒製茶機械の失敗が証明されてしまいました。謙三は機械代金も満足に支払ってもらえず、経済的苦境に陥ってしまいます。
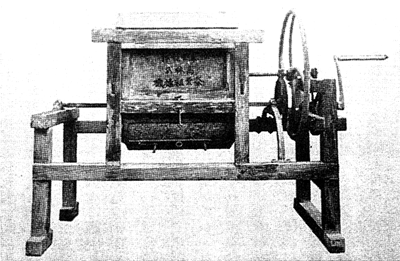 |
|
茶葉粗揉機
|
茶葉揉乾機の発明
 自立軒製茶機械が失敗したうえ類焼で自宅を焼失した謙三は、明日の暮らしにも事欠く中にあっても、機械の発明を続けていきました。
明治26年、農商務省農務局のはからいで、染井の藤堂屋敷内に広い研究用製茶工場を設けました。そして、明治28年、手揉みの動作を機械内部に備え付けた「茶葉揉乾機」を思いつき、試作を重ねて明治30年に完成させました。この機械は
粗揉機として発売されて各地で予想以上の好評を得て注文が相次ぎ、謙三はうれしい悲鳴をあげるほどの忙しさとなりました。この茶葉揉乾機は、明治31年12月、茶葉粗揉機として特許第3301号を取得しています。 自立軒製茶機械が失敗したうえ類焼で自宅を焼失した謙三は、明日の暮らしにも事欠く中にあっても、機械の発明を続けていきました。
明治26年、農商務省農務局のはからいで、染井の藤堂屋敷内に広い研究用製茶工場を設けました。そして、明治28年、手揉みの動作を機械内部に備え付けた「茶葉揉乾機」を思いつき、試作を重ねて明治30年に完成させました。この機械は
粗揉機として発売されて各地で予想以上の好評を得て注文が相次ぎ、謙三はうれしい悲鳴をあげるほどの忙しさとなりました。この茶葉揉乾機は、明治31年12月、茶葉粗揉機として特許第3301号を取得しています。
 この機械の後援を続けてきた東京西ヶ原農事試験場の大林雄也技師は、日本一の茶師と言われた榛原郡初倉村(現・島田市)の大石音蔵と謙三の茶葉揉乾機を対決させました。結果は、能率的にはもちろん、品質においても機械の圧勝でした。大石音蔵は、それまで機械を見くびっていましたが、対決の三日後に謙三を訪ね「あの機械を譲って欲しい」と願い出て、明治31年に改良された茶葉揉乾機を郷里の初倉に持ち帰りました。 この機械の後援を続けてきた東京西ヶ原農事試験場の大林雄也技師は、日本一の茶師と言われた榛原郡初倉村(現・島田市)の大石音蔵と謙三の茶葉揉乾機を対決させました。結果は、能率的にはもちろん、品質においても機械の圧勝でした。大石音蔵は、それまで機械を見くびっていましたが、対決の三日後に謙三を訪ね「あの機械を譲って欲しい」と願い出て、明治31年に改良された茶葉揉乾機を郷里の初倉に持ち帰りました。
|
|